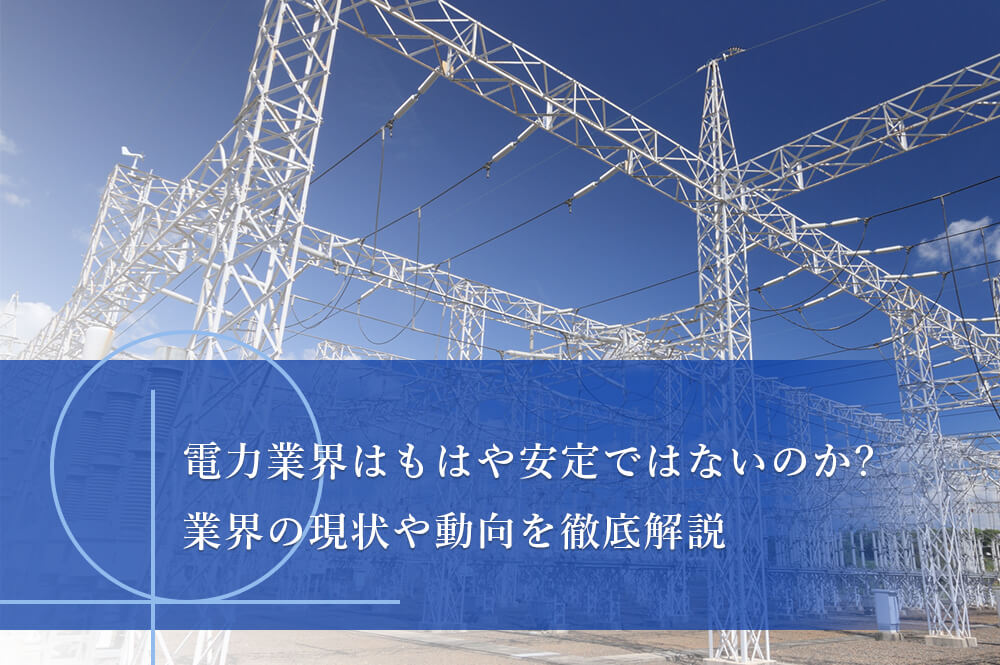

竹内 健登
Kento Takeuchi
東京大学工学部卒。大手一流ホワイト企業の内定請負人。就活塾「ホワイトアカデミー」を創立・経営。これまで800人以上の就活をサポート。塾はカリキュラムを消化した塾生のホワイト企業内定率100%を誇り、カリキュラムを消化したにもかかわらず、ホワイト企業の内定が出なければ費用を全額返金する返金保証制度を提供中。2019年に『子どもを一流ホワイト企業に内定させる方法』(日経BP刊)を出版し、「親が子育ての集大成である"就活"に臨む際の必読書」、「これができれば本当に一流企業に内定できる」と話題。塾のYouTubeチャンネルではホワイトな業界の紹介や大手企業の倍率、ESの添削を公開するなど塾の就活ノウハウを一部紹介している。
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCm1vSnSBj7kksfi8GIBnu0g
目次 非表示






| 電源 | 構成比 |
|---|---|
| 原子力 | 6.90% |
| 石炭 | 31.00% |
| 天然ガス | 34.40% |
| 石油等 | 7.40% |
| 水力 | 7.50% |
| 太陽光 | 8.30% |
| 風力 | 0.90% |
| 地熱 | 0.30% |
| バイオマス | 3.20% |
九州電力は、太陽光などの再生可能エネルギーを主力電源化するとともに、電力の需要に応じて機動的に発電量を増減できる火力発電を調整役として引き続き重視していく方針を示しています。
2050年のカーボンニュートラル実現に向けて、余剰再生エネを有効活用する「蓄電」と、火力発電などで出た二酸化炭素(CO2)を地中に貯留する「CCS」の実用化は大きなカギとなります。
電池スタートアップのARM Technologies(相模原市緑区)はアイシンと共同で、電気を充放電できる持ち運び可能な液体を開発した。
「液体電池」と呼ばれるもので、ガソリンのように船に積んで輸送できたり、電気自動車(EV)に注入して使えたりすることができる。低コストで発電された海外のエネルギーを液体電池で輸送すれば、国内で発電するより安くなると試算する。
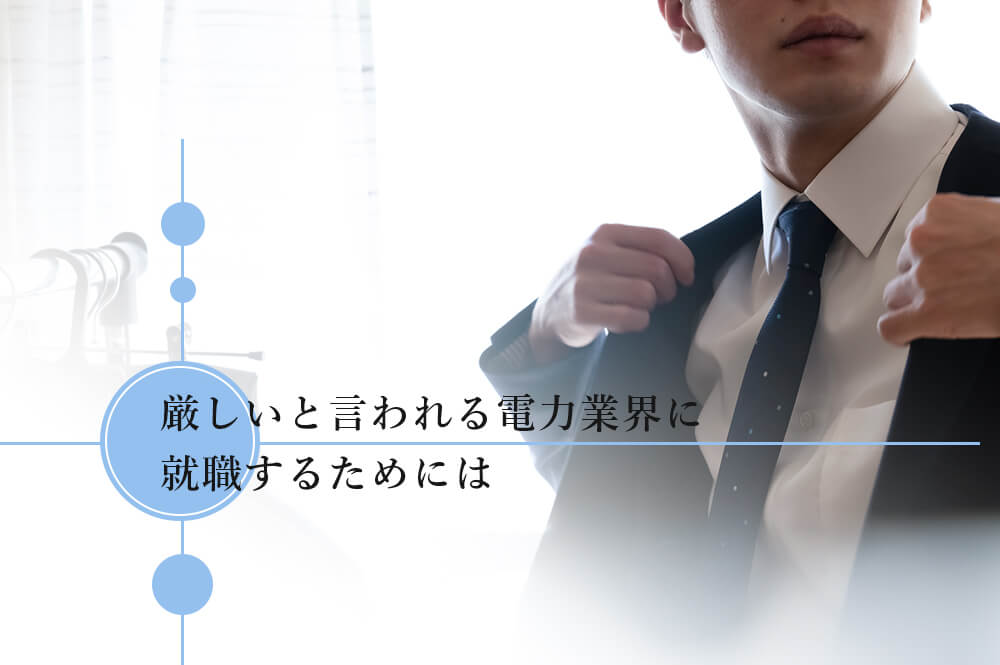
ホワイトアカデミーとは?
